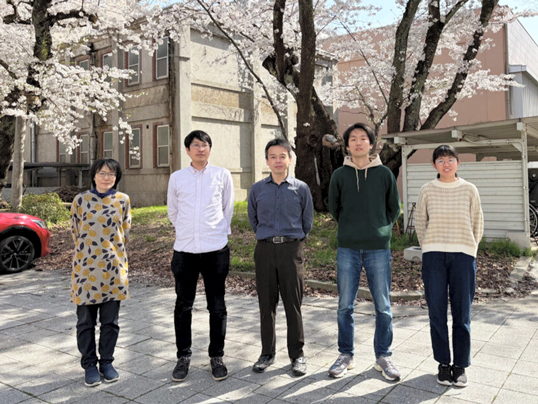
ISSN: 0037-3796
日本神経化学会
The Japanese Society for Neurochemistry
© 2025 日本神経化学会© 2025 The Japanese Society for Neurochemistry
2024年7月より金沢大学医薬保健研究域医学系先鋭科学融合研究分野の教授を拝命致しました齋藤敦と申します。この度は日本神経化学会の機関紙で研究室紹介の機会を頂き、厚く感謝申し上げます。先鋭科学融合研究分野は、私の着任に伴って新設された基礎系講座です。まだ構成メンバーは少ないですが、メリハリのある明るい研究室運営を目指しています。
私は2005年に北海道大学薬学部総合薬学科(薬理学研究室:野村靖幸教授)を卒業し、博士前期課程は奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科(細胞構造学講座:塩坂貞夫教授)の下で学び、博士課程は宮崎大学大学院医学系研究科(分子細胞生物学分野:今泉和則教授)に進学しました。節目を迎える度に所属が変わりましたが、どの先生にも温かいご指導を賜りました。日本神経化学会に入会したのは2005年9月なので、当時は博士前期課程1年生になります。直後に開催された第48回日本神経化学会大会(福岡)に参加しました。私にとっては初めて入会し、大会に参加した学会が神経化学会であり、大変思い入れのある学会です。当時は大会で何を勉強すればよいのかさえもよくわからず右往左往していましたが、それからほぼ毎年、大会に参加させて頂くうちに顔見知りの先生も増え、いつも楽しく過ごしています。第51回日本神経化学会大会(富山)では博士課程2年の学生でした。この時に第1回若手育成セミナーにも参加し、その際のセミナー参加学生や講師の先生とは今でも交流が続いています。その後、評議員や将来計画委員会などの学会運営にも参画させて頂くようになり、第66回日本神経化学会大会(神戸)ではプログラム委員会にも加えて頂きました。大変な仕事でしたが貴重な経験を積ませて頂いたと思っています。
私の研究のバックグラウンドを申し上げると、神経系というよりは小胞体の機能解析、特に小胞体ストレスとその応答系の研究に、北海道大学時代から一貫して携わっています。ターゲットとしているのは、小胞体ストレスセンサー分子であり、その中でもアストロサイトで特異的に発現するOASISと、神経細胞で強く発現するBBF2H7です。神経系の細胞に発現しているこれらセンサー分子の機能を解析するために、神経化学会大会でも多くのことを勉強させて頂きました。ところが博士課程在籍時にご指導頂いた今泉和則先生の下で遺伝子欠損マウスの解析を開始すると、OASIS欠損マウスは骨組織、BBF2H7欠損マウスは軟骨組織の形成が障害されており、手探りで骨格組織の解析に取り掛かりました。生理的条件下で発生する「細胞機能に必須の小胞体ストレス」という概念をまとめ、何とか博士号を取得した後は、今泉和則先生に宮崎大学で助教として採用して頂きました。その後も広島大学で同じく助教、2014年から2016年にかけて一度米国Washington University in St. Louis, Department of Neuroscienceに留学して久しぶりに神経系分野を満喫致しましたが、再び広島大学に戻り、准教授として2024年6月まで今泉和則先生にご指導頂きました。交流は2025年現在で20年目に入りますが、その間に神経化学だけでなく解剖学や生化学を学ばせて頂き、脳、骨軟骨、脂肪、筋といった様々な組織の解析に触れることができました。
金沢大学でも、小胞体ストレスとその応答系の解析が中心にあります。しかしながら小胞体機能の役割も、もはや小胞体のみで完結するものではないことは明白です。そこで現在は、小胞体を中心としたオルガネラ間の機能連携の仕組みを理解することを目指しています。そしてその破綻が、アストロサイトの増殖亢進によるgliosisの制御異常や膠芽腫などの発症につながることもわかってきており、治療標的としての可能性を日々探っています。技術的には培養細胞および遺伝子改変マウスを用いて主に生化学的、分子細胞生物学的解析を駆使しています。それに加えてイメージング解析やゲノム・エピゲノム編集技術、タンパク質の構造解析、in silico解析なども積極的に活用しています。開設されたばかりの研究室なのでメンバーはまだ少ないですが、少しずつ学生も見学に訪れてくれるようになっており、より活気ある研究室を目指しています。そして何よりも金沢大学に所属しておられる研究者の皆様は親切かつ研究レベルが高いことに感銘を受けています。共通設備も非常に充実しており、学内のセミナーは常に議論が活発で、医学・生命科学の枠を超えた理工・人文学などとの交流と異分野融合も盛んな大学だと思います。私も皆様の研究熱に圧倒されながら、遅れをとらぬよう日々身の引き締まる思いです。
末筆ながら、これまでご指導賜りました多くの先生方、いつもサポートしてくれている研究室メンバーに厚く御礼申し上げます。私も研究室も、神経化学に触れながらその技術はまだまだ未熟です。今後とも日本神経化学会の先生方におかれましては、ご指導・ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
This page was created on 2025-07-02T17:39:02.132+09:00
This page was last modified on 2025-08-19T14:54:01.000+09:00
このサイトは(株)国際文献社によって運用されています。